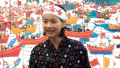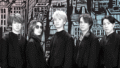憂歌団とは――日本ブルース界の伝説
憂歌団(ゆうかだん)は、日本のブルース・バンドの草分け的存在であり、1970年代から活動を続ける伝説的なグループです。大阪を拠点に、ブルースを日本語で歌い上げる独自のスタイルを確立し、関西ブルースシーンを牽引しました。彼らのバンド名は「ブルース・バンド」を日本語に意訳したもので、「エレジーが『哀歌/挽歌』ならば、ブルースは『憂歌』である」という発想から名付けられました。
1975年に「おそうじオバチャン」でデビューし、その後もスリーピー・ジョン・エスティスやマディ・ウォーターズといった本場アメリカのブルース巨人たちとも共演。日本一のブルース・バンドとして長年君臨し続け、1998年に一度活動を休止したものの、2013年に再結成。日本の音楽シーンにおけるブルースの普及と発展に多大な影響を与えた存在です。
憂歌団のメンバー構成とプロフィール
憂歌団のオリジナルメンバーは以下の4人です。
木村充揮(きむら あつき)
ボーカル・ギター担当。本名:木村秀勝(または朴秀勝)。1954年3月24日生まれ、大阪府大阪市生野区出身。独特のハスキー・ボイスは「天使のダミ声」と称され、バンドの顔ともいえる存在です。
内田勘太郎(うちだ かんたろう)
リードギター・ボーカル担当。本名:内田昌宏。1954年1月22日生まれ、大阪府大阪市出身。卓越したギタープレイでバンドサウンドを支えます。
花岡献治(はなおか けんじ)
ベース・ボーカル担当。本名:花岡憲二。1953年7月27日生まれ、大阪府大阪市出身。2024年6月17日に逝去。
島田和夫(しまだ かずお)
ドラム担当。1953年生まれ。2012年に逝去。
現在は、元RCサクセションの新井田耕造(1953年3月25日生まれ、東京都台東区出身)がドラマーとして加入し、木村・内田・新井田の3人体制で活動しています。
憂歌団の音楽の特徴とジャンル「ブルース」について
憂歌団の音楽は、アメリカ南部発祥のブルースをベースに、日本語の歌詞と関西・大阪の土着的なユーモアや哀愁を融合させた「日本語ブルース」として独自の地位を築いています。
大阪弁の歌詞と日常感
彼らの楽曲は大阪弁による歌詞が特徴で、パチンコ、酔っ払い、ドロボーなど庶民的で卑俗な題材をユーモラスかつ親しみやすく描写。1970年代のワーキングクラスの日常や不満、ぼやきを切り取ることで、多くの日本人に共感と親近感を与えました。
音楽性の独自性
ブルースの基本である3コード進行を踏襲しつつも、時には4コードのラグタイム調を取り入れるなど、単なる模倣ではなく、歌謡曲やフォークとも異なる“憂歌団スタイル”を確立しました。他の関西ブルースバンドが「本場にどれだけ近づけるか」を目指すのに対し、憂歌団は押し付けがましさのない粋なアプローチで、まさに“ジャパン・オリジナル”な音楽を生み出しています。
ブルースというジャンルについて
ブルースはアメリカ南部の黒人社会にルーツを持つ音楽で、哀愁や悲しみ、人生の苦しみを歌うジャンルです。憂歌団はこの「憂い(ブルース)」を日本語と大阪文化で表現し、「ブルース=憂歌」として独自の世界観を築きました。
代表曲と影響
「おそうじオバチャン」や「嫌んなった」など、放送禁止となるほど強烈なインパクトを持つ楽曲も多く、後の日本のロックバンドやシンガーソングライターにも大きな影響を与えています。
木村充揮と内田勘太郎――出会いからバンド結成まで
憂歌団の中心人物である木村充揮と内田勘太郎は、関西ブルースシーンの伝説となるバンドを生み出した名コンビです。二人の出会いからバンド結成までのストーリーには、偶然と必然が交錯する青春のドラマがありました。
二人の出会いと高校時代
木村充揮(きむら あつき)と内田勘太郎(うちだ かんたろう)は、共に大阪市生野区出身。二人が出会ったのは高校時代、大阪府立今宮工業高校の軽音楽部がきっかけでした。
当時、木村は中学時代からギターを弾き始め、独特のハスキーボイスで歌うことを楽しんでいました。一方、内田もギターに夢中で、ブルースやロックに心酔していた青年でした。軽音楽部で出会った二人は、すぐに意気投合。お互いの音楽的センスに惹かれ合い、放課後や休日には一緒に音楽談義をしたり、ギターを持ち寄ってセッションを重ねるようになります。
学校の枠を超えて、地元のライブハウスや喫茶店で演奏することも増え、次第に「自分たちのバンドを作りたい」という思いが強まっていきました。
憂歌団誕生のきっかけと初ライブ
1970年代初頭、木村と内田は同じく大阪出身の花岡献治(ベース)、島田和夫(ドラム)と出会い、4人でバンドを結成します。バンド名を「憂歌団」としたのは、「ブルース」を日本語で表現したいという思いから。「哀歌」や「挽歌」ではなく、「憂歌(ブルース)」という言葉が彼らの音楽性にぴったりだったのです。
憂歌団としての初ライブは、1975年、大阪のライブハウス「難波ロケッツ」で行われました。当時はまだアマチュアバンドでしたが、木村の唯一無二の歌声と、内田の卓越したギター、そして関西弁のユーモアあふれるパフォーマンスが話題となり、瞬く間に地元で評判を呼びます。
その後、彼らはブルースを日本語で表現するという独自のスタイルを武器に、1975年にシングル「おそうじオバチャン」でメジャーデビュー。以降、日本ブルース界の伝説として、長きにわたりシーンを牽引していくことになります。
憂歌団誕生と初期の活動
初期メンバーの加入と活動拠点
憂歌団は1970年、木村充揮と内田勘太郎の二人によって結成されました。最初のステージは、大阪府立工芸高等学校の文化祭で、ここからバンドとしての歩みが始まります。1975年のデビューから1998年の「冬眠」宣言まで、不動のメンバーで活動を続けました。
活動拠点は大阪で、特に高校卒業後は阿倍野の喫茶店などで定期的にライブを行い、関西ブルースシーンの中心的存在となっていきます。
デビューと「おそうじオバチャン」
憂歌団は1975年10月1日、トリオレコードのSHOW BOATレーベルからシングル「おそうじオバチャン」でデビューしました。この曲は大阪弁によるユーモラスな歌詞と、ブルースの要素を取り入れた独自のサウンドで大きな話題となりましたが、歌詞が「掃除婦に対して差別的」との理由で、発売からわずか1週間後に放送禁止処分を受けています。
それでも「おそうじオバチャン」は憂歌団を象徴する代表曲となり、彼らの名を全国に知らしめるきっかけとなりました。同年にはファーストアルバム『憂歌団』もリリースし、深い味わいのある木村のボーカルと内田のギターを軸に、独自の日本語ブルースを確立。以降も関西を拠点に、全国的な人気を獲得していきました。
憂歌団とブルース――日本語ブルースの確立
憂歌団サウンドの特徴と影響
憂歌団は、1970年代の日本においてブルースを日本語で表現することにこだわり、独自の「日本語ブルース」を確立したバンドです。彼らのサウンドは、関西弁による日常のユーモアや哀愁を盛り込んだ歌詞、アコースティック主体のブルースサウンド、そして木村充揮のハスキーなボーカルと内田勘太郎の渋いギターが特徴です。
多くの日本のブルースバンドが洋楽カバー中心だった時代、憂歌団はオリジナルの日本語ブルースに徹し、歌謡曲やフォークとも異なる独自の音楽性を発展させました。その姿勢とサウンドは、後の日本のロックバンドやシンガーソングライターに大きな影響を与えています。
関西ブルースシーンとの関わり
憂歌団は、1970年代の「関西ブルース・ブーム」の中心的存在でした。京都や大阪を拠点に、ウエスト・ロード・ブルース・バンドや上田正樹とサウス・トゥ・サウスなどと並び、関西のブルースシーンを牽引しました。
当時の関西は、学生運動や労働者文化の影響もあり、反体制的で自由な空気が流れていました。ブルースの「不満」や「ぼやき」といった感情が、関西の庶民的な感覚と共鳴しやすかったことも、憂歌団の音楽が広く受け入れられた理由の一つです。
大阪のイメージが強いブルースバンド「憂歌団」だが、意外にもそのルーツには京都が大きく関わっていた。ソロとしては初のライブ盤アルバムをリリースしたばかりのボーカル木村充揮が、9月に大阪城音楽堂で「木村充揮ロックンロールフェスティバル」が開催されるのを前に、京都への思いを語っています。(京都新聞)
「よう京都のバンドと言われましたわ」。1972年、高校の同級生だった内田勘太郎と組んだ「憂歌団」は、2人の地元である大阪・天王寺の喫茶店で初めてライブを行った。ともに18歳だった。しかし、高校を卒業して活動を休止していた頃、京都の銀閣寺近くにある店「ダムハウス」を知人に紹介された。
「当時、京都はブルースが盛り上がっていたんですわ。で、『2人でやらせてもらえませんか』って行った。僕はまだ家の仕事をしてたからライブ終わって最終電車で天王寺に帰ったけど、勘太郎はフリーだったから、京都の友達の所に泊めてもらったりして」
京都ではブルースバンドが次々と生まれ、「村八分」や豊田勇造さんのような先駆者もいて、大きな渦が生まれ始めていたという。「イベントもぎょうさんあって、(京都大の)西部講堂でもライブが多かった。学生がみんなよう(酒を)飲んでて、ライブ中に一升瓶が回ってきて。学生を中心に大阪よりも活発な雰囲気があったんです」
73年、京都市にライブハウス「拾得[じっとく]」(上京区)が開店。翌年には「磔磔[たくたく]」(下京区)が続き、「サーカス&サーカス」も銀閣寺近くにできた。「憂歌団」もライブに出演するようになった。「やっぱり、人の巡り合わせいうんかね。京都で歌うようになって、次のライブとかレコーディングにつながっていく。『拾得』と『磔磔』が今もあるいうんが、ものすごくうれしい」。7月29日から6日間は「磔磔」で毎日ゲストを招いてライブを開いた。
今も大阪・天王寺に住む「こてこて」の大阪人である木村さんにとって、京都とはどんな街なのだろう。「大阪は大衆的で、がさつな所がある(笑)。大阪の方がブルース的だとは思うけど、京都でのライブでは、お客さんの酒の入り方次第ではすごい時もある。大阪も京都も、あんまり変わらへんのちゃうかな」
ライブでは歌の合間に水割りをチビチビ飲みながら、ちゃめっ気たっぷりのしゃべりで笑わせる木村。「でも、京都の街はあんまり歩いたことないんです。ライブの合間はパチンコばっかりで。すいません」。おなじみの“木村節”で笑いながら語った。
私も大学時代、ロックbluesが好きで良く拾得やライブハウス、京大西部講堂や円山野外に出入りしていました。
憂歌団との出会いは拾徳でした。ビール樽を逆さまにした椅子にでかいテーブル、昔の倉を改造した古びたステージでした。『アホの木村ぁー、また来たでー、はよ演奏せーや!!』『じゃかましゃい!大人しい待っとれー』で始まります。『先週なぁ また東京からbluesやろいうて、ぎょうさん来よってん、ほんでみんなしょんべんちびって帰っていきよったわ』それから暫くは私も東京の澄ました音楽が好きになれなかった。
また、名古屋の尾関ブラザーズなど、他地域の日本語ブルースの先駆者たちとも交流し、彼らからの影響も受けつつ、憂歌団ならではの音楽性を磨いていきました。
代表曲・名盤の紹介
憂歌団の代表曲・名盤は以下の通りです。
「おそうじオバチャン」:デビュー曲。大阪弁によるユーモラスな歌詞が話題となり、放送禁止にもなった伝説の一曲。
「嫌んなった」:4コードのラグタイム調で、失恋を明るく歌い上げる名曲。
「パチンコ」:働く庶民の哀歓を描いた代表作。
「出直しブルース」:ホーンやストリングスを取り入れ、音楽性の幅を広げた中期の名曲。
アルバム『憂歌団』(1975):ファーストアルバムで、初期の代表曲が多数収録。
ライブ盤『生聞59分』:ライブバンドとしての魅力が詰まった傑作。
アルバム『夢・憂歌』:ポップスやジャズの要素も取り入れた洗練された一枚。
憂歌団と「在日」キーワードの背景
憂歌団と社会の背景
憂歌団の音楽は、1970年代の日本社会、特に都市部のワーキングクラスの日常や不満、社会の片隅で生きる人々のリアルな感情を大阪弁で描き出しました。ブルースというジャンル自体がアメリカの黒人社会の差別や疎外感から生まれた音楽であり、憂歌団もまた「社会の周縁」にいる人々の声を代弁してきました。
「在日」との関連についての考察
憂歌団のリードボーカル・木村充揮は、本名を朴秀勝(パク・ススン)といい、在日韓国人であることを公表しています。この事実は、彼自身やバンドの音楽性に直接的な影響を与えたとされることもありますが、憂歌団の活動や楽曲の中で「在日」であることを前面に押し出すことは基本的にありませんでした。
ただし、在日コリアンとしての出自や、戦後日本社会でのマイノリティ体験が、木村の「憂い」や「哀愁」を帯びた歌声、社会の片隅にいる人々への共感、そしてブルースというジャンルへの強い親和性につながっていると見ることもできます。
また、憂歌団の音楽が社会の底辺やマイノリティの視点を描くことが多いのは、ブルースという音楽の本質と、メンバーのバックグラウンドが自然に重なった結果とも言えるでしょう。
憂歌団は、日本語ブルースのパイオニアとして、関西のブルースシーンを牽引し、社会の片隅に生きる人々のリアルな感情を音楽で表現してきました。リーダー木村充揮の「在日」という背景も、彼らの音楽に奥深い共感とリアリティを与えています。
メンバーのその後と再結成の経緯
憂歌団は1998年に「冬眠」(活動休止)を宣言し、メンバーはそれぞれソロ活動へと移行しました。木村充揮は独特の歌声を活かし、ソロシンガーとしてジャンルを超えた幅広い活動を展開。内田勘太郎もソロギタリストとしてブルース、ロック、ジャズなど多彩な音楽性を追求し、両者ともに「憂歌兄弟」としてのユニット活動も行いました。
2012年にはオリジナルメンバーのドラマー、島田和夫が逝去。その翌年、島田の追悼イベントをきっかけに、憂歌団は約15年ぶりに再結成を発表します。2013年8月には「情熱大陸SPECIAL LIVE SUMMER TIME BONANZA’13」への出演で活動再開をお披露目し、9月には「憂歌団からの便り。〜島田和夫祭り〜」と題した復活ライブを開催。ここではオリジナルメンバー3人に加え、複数のゲストドラマーを迎えた特別編成で演奏しました。
同年12月には元RCサクセションの新井田耕造が正式にドラムとして加入し、新体制での活動が本格化します。
近年の活動と最新情報
再結成後の憂歌団は、ライブ活動を中心に精力的な活動を再開。2014年には「憂歌兄弟」としてフルアルバムを発表し、憂歌団としても各地の音楽フェスやワンマンライブに出演しています。ライブでは往年の名曲に加え、新たなアレンジやカバーも披露し、世代を超えたファンから支持を集めています。
また、木村充揮と内田勘太郎はソロや「憂歌兄弟」としても並行して活動し、それぞれの個性を活かした音楽活動を展開。憂歌団としては、近年も過去作のリマスター盤やライブDVDのリリースが続き、日本ブルースの伝説として存在感を保っています。
2024年6月には、ベースの花岡献治が逝去。花岡は晩年、熊本を拠点に活動していました。今後も憂歌団は、現メンバーでライブや音源リリースなどを継続していくとみられます。
憂歌団が与えた影響と現在
日本音楽界への影響
憂歌団は、日本における「日本語ブルース」のパイオニアとして、1970年代以降の音楽シーンに大きな影響を与えました。大阪の生活感やユーモアを盛り込んだ歌詞、関西弁によるリアルな表現、そして木村の唯一無二のボーカルとメンバーの卓越した演奏は、後進のミュージシャンに多大なインスピレーションを与えています。
彼らのスタイルは、ブルースというジャンルを日本の大衆音楽に根付かせ、ロックやフォーク、J-POPなど幅広いジャンルのアーティストに影響を及ぼしました。特にライブパフォーマンスの熱量や、歌詞のリアリティは、多くの若手アーティストからもリスペクトを集めています。
憂歌団の現在とこれから
現在の憂歌団は、木村充揮、内田勘太郎、新井田耕造の3人体制で活動を継続中です。ライブやフェスへの出演、過去作のリイシュー、そして「憂歌兄弟」やソロ活動などを通じて、日本のブルース文化の継承と発展に貢献しています。
2024年に花岡献治が亡くなったことで、オリジナルメンバーは2人となりましたが、憂歌団の音楽と精神は今も受け継がれています。今後もライブ活動や音源リリースを続け、時代や世代を超えて“日本語ブルース”の魅力を発信し続けていくことが期待されています